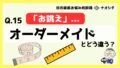お悩み
Q.衣の袖に蝋燭や線香の火が当たり、穴が空いてしまいました。修繕できますか?
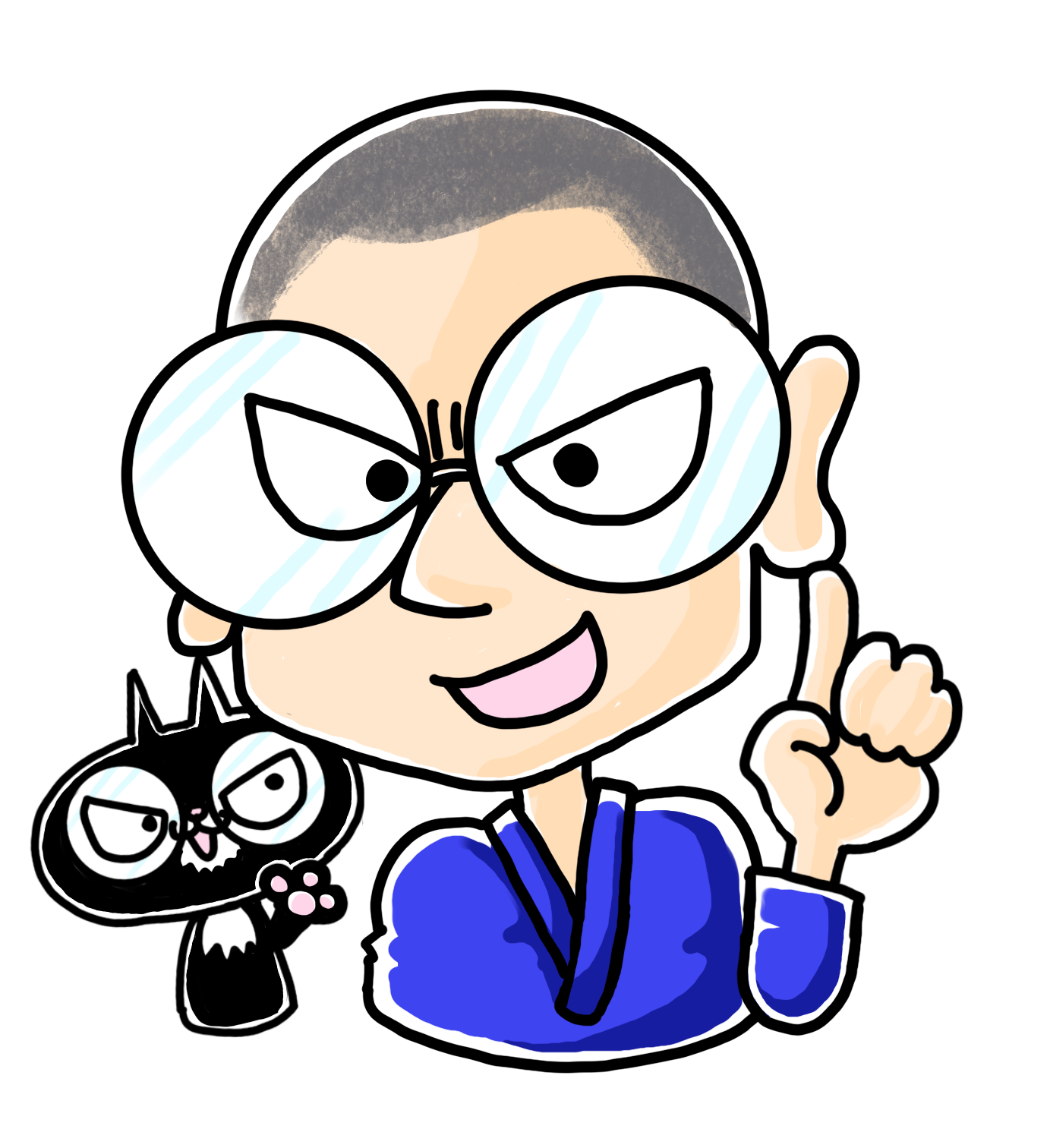
回答
A.状態に応じて、主に3つの対処法があります。
仏事や法要の場では、蝋燭や線香の火に法衣が近づくことも少なくありません。気づかないうちに袖口が火に近づき、火が触れてしまうケースが見られます。
その中でも多いのが「袖に蝋燭や線香があたり、焦げて穴が空いてしまった」というご相談です。
とくに現在多く用いられている化繊(ポリエステル系)素材の法衣は、熱に非常に弱く、一瞬の接触でもすぐに穴が空いてしまいます。火が直接当たらずとも、近づいただけで表面が溶ける場合もあります。
このような火による損傷への対処法として、ナオシチでは以下の3つの方法を状況に応じて使い分けています。
① 焦げた部分を糸で縫って塞ぐ
② 裏から生地を当てて縫う
③ 袖をまるごと新しいものに取り替える
① 焦げた部分を糸で縫って塞ぐ
もっとも簡易的な方法は、焦げた部分を丁寧に取り除き、同系色の糸で塞ぐことです。穴が比較的小さい場合や、目立ちにくい箇所であれば、この方法で充分きれいに修繕できます。
ただし、焦げた生地は強度が著しく低下しているため、そのまま縫おうとしても縫えないことがあります。そこで修繕の際は、焦げた周辺を慎重に取り除き、丈夫な生地部分を縫う必要があり、実際には熟練の判断が求められます。
② 裏から生地を当てて縫う
穴がある程度の大きさで、かつ袖全体を取り替えるほどではない場合は、裏から同じ色・種類の布(または近似の布)をあて、補強してから縫う方法をとります。
この方法では、穴の周囲に補強布を縫い付け、生地の強度を確保するため、使用時の動きにも耐えやすくなります。外から白衣が透けて見える心配もなくなり、見た目の印象も改善されます。
ただし、表面に細かな縫い目が見えるため、近くで見ると修繕跡がわかることがあります。とはいえ、遠目からはほとんど気づかれず、実用上は問題ないと判断されることが多い方法です。
③ 袖をまるごと新しいものに取り替える
見た目の仕上がりを重視される場合や、穴が大きく、①②の方法では対応が難しい場合には、袖を新たに作り直して取り付けるという方法をとります。
この方法は、仕上がりがもっとも美しく、縫い目や補修跡も残りません。ただし注意点として、元の本体と新しい袖で、染めや織りの時期が違う場合、微妙な色の差が出ることもあります。また、使用頻度の違いによる生地のへたり具合も違うこともあるため、慎重な判断が必要です。
特に古い法衣や、代々受け継がれた貴重な袈裟の場合は、現物確認のうえ、最適な方法をご提案しております。
修繕をご検討の方へ ― まずは触らず、ご相談ください
穴が空いているのを見つけると、「とりあえず何かで塞いでおこう」「自分で縫ってみよう」と思われるかもしれませんが、焦げた生地は想像以上にもろく、自己修理によって穴が広がってしまうリスクがあります。
また、生地の方向や織りの伸縮に対する配慮なく縫ってしまうと、修繕が難しくなってしまうこともあるため、まずは触らず、ナオシチへご相談いただくことをオススメしています。
LINEやメールで写真を添付送信いただくか、ご予約のうえ、実物をナオシチにお持ち込みいただければ、より正確に修繕方法をご提案可能です。
いずれにせよ、できるだけ早めにご相談いただくことが、結果的に法衣を長持ちさせる一番の方法です。
法衣袈裟の洗濯修繕は直七法衣店まで
ナオシチでは、長年にわたり法衣袈裟の仕立てと修繕を手がけてきました。焦げ・やぶれ・ホツレなど、状態に応じて最適な方法をご提案いたします。
「こんな状態でも直せるだろうか?」「どこまで元に戻せるのか?」など、不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
ナオシチ公式LINEからのご相談も、随時受け付けております。
<ナオシチ公式LINEはこちら>
https://s.lmes.jp/landing-qr/1661111355-glJ4nGYw?uLand=GsXhu1