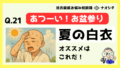直七法衣店4代目ナオシチです。今日もみんなで袈裟功徳について学んでいきましょう。
3択クイズにチャレンジ!答えは最後に。
この記事では、ある大切なことを知らないと「ある生き物」よりも愚かだと説かれています。さて、その「ある生き物」とは、次のうちどれでしょう?
- A) 畜類(動物)
- B) 龍神
- C) 餓鬼
答えは記事の最後に!
原文
「まことにわれら辺地 (ヘンチ) にうまれて末法 (マッポウ) にあふ。うらむべしといへども、仏仏嫡嫡相承 (チャクチャクソウジョウ) の衣法 (エホウ) にあふたてまつる、いくそばくのよろこびとかせん。」
「いづれの家門かわが正伝のごとく、釈尊の衣法ともに正伝せる。これにあふたてまつりて、たれか恭敬 (クギョウ) 供養 (クヨウ) せざらん。たとひ一日に無量恒河沙 (ムリョウゴウガシャ) の身命 (シンミョウ) をすてても、供養したてまつるべし。なほ生生世世 (ショウジョウセゼ) の値遇頂戴 (チグウチョウダイ) 、供養恭敬を発願 (ホツガン) すべし。」
「われら仏生国 (ブッショウコク) をへだつること、十万余里の山海はるかにして、通じがたしといへども、宿善 (シュクゼン) のあひもよほすところ、山海に擁塞せられず、辺鄙 (ヘンピ) の愚蒙 (グモウ) きらはるることなし。」
「この正法 (ショウボウ) にあふたてまつり、あくまで日夜に修習 (シュジュウ) す。この袈裟を受持 (ジュジ) したてまつり、常恒 (ジョウゴウ) に頂戴護持 (チョウダイゴジ) す。」
「ただ一仏二仏のみもとにして功徳を修せるのみならんや、すでに恒河沙等の諸仏のみもとにして、もろもろの功徳を修習せるなるべし。たとひ自己 (ジコ) なりといふとも、たふとぶべし、随喜 (ズイキ) すべし。祖師伝法 (ソシデンポウ) の深恩 (ジンノン) 、ねんごろに報謝すべし。」
「畜類 (チクルイ) なほ恩を報ず、人類 (ジンルイ) いかでか恩をしらざらん。もし恩をしらずば、畜類よりも愚なるべし。」
現代語訳
本当に私たちは、辺境の地(日本)に生まれて末法の時代に出会いました。嘆くべきことではありますが、仏から仏へ、祖師から祖師へと正しく伝えられてきた衣(袈裟)と法に出会うことができたのは、どれほどの喜びでしょうか。
どの宗派が、私たちの正伝の宗派のように、釈尊の衣と法を共に正しく伝えてきたでしょうか。この衣と法に出会うことができて、誰がうやまい供養しないでいられましょうか。たとえ一日にガンジス川の砂の数ほど多くの命を捨てても、供養すべきです。さらに、いつの世に生まれてもこれに出会い、頭上に戴いて敬い、供養しうやまうという願いを起こすべきです。
私たちは、釈尊の生まれた国(インド)から十万余里も離れた、山や海を越えた遠い地にいて、釈尊の国へは簡単に行くことができません。しかし、過去世からの善行が引き起こしたことによって、山や海にさえぎられることもなく、辺境の知識のない人間として嫌われることもなく、この正法は伝えられました。
そして私たちは、この正法に出会うことができ、思う存分日夜に修行しています。この袈裟を受け継ぎ、常に頭上に戴いて大切に護持しています。
これは、私たちがただ一仏や二仏のもとで功徳を修めただけではなく、すでにガンジス川の砂の数ほど多くの諸仏のもとで、様々な功徳を修行してきた結果に違いありません。
たとえ自分のことではあっても、これを尊び、共に喜ぶべきです。祖師が法を伝えてくれた深い恩に、心から感謝し報いるべきです。
動物でさえ恩に報いるのですから、人間がどうして恩を知らないことがありましょうか。もし恩を知らなければ、動物よりも愚かであると言えるでしょう。
語句説明
- 辺地(ヘンチ):文化や文明の中心地から離れた辺境の土地。ここでは日本を指す。
- 末法(マッポウ):仏法が衰え、修行によって悟りを得ることが難しくなった時代。
- 嫡嫡相承(チャクチャクソウジョウ):嫡子から嫡子へと、正統な後継者に代々法が伝えられること。
- 衣法(エホウ):衣(袈裟)と法(仏教の教え)のこと。
- 恭敬(クギョウ)供養(クヨウ):うやまい敬い、供え物をして奉仕すること。
- 無量恒河沙(ムリョウゴウガシャ):ガンジス川の砂の数のように、非常に多い数を表す仏教用語。
- 身命(シンミョウ):身体と生命。
- 生生世世(ショウジョウセゼ):生まれては死に、また生まれるという輪廻を繰り返す永劫の世。
- 値遇頂戴(チグウチョウダイ):尊いものに出会い、頭上に戴いて敬うこと。
- 発願(ホツガン):仏や菩薩に対して願いや誓いを立てること。
- 仏生国(ブッショウコク):釈迦牟尼仏が生まれた国、インドを指す。
- 宿善(シュクゼン):過去世に積んだ善い行い。それが原因となって現世に良い結果をもたらす。
- 辺鄙(ヘンピ)の愚蒙(グモウ):辺境に住む、知恵や教えのない人々。
- 正法(ショウボウ):仏の正しい教え。
- 修習(シュジュウ):仏道を修行し、学び習うこと。
- 受持(ジュジ):教えや戒律などを受け継ぎ、心に保つこと。
- 常恒(ジョウゴウ):常に変わらないこと。
- 頂戴護持(チョウダイゴジ):頭上に戴いて敬い、大切に守り持つこと。
- 自己(ジコ):自分自身。
- 随喜(ズイキ):他人の善行や功徳を見て、自分のことのように共に喜ぶこと。
- 祖師伝法(ソシデンポウ)の深恩(ジンノン):仏祖や歴代の祖師が仏法を正しく伝えてくれた、非常に深い恩。
- 畜類(チクルイ):人間以外の動物。
- 人類(ジンルイ):人間。
詳細な解説
辺境の末法に生まれた奇跡
原文は「まことにわれら辺地にうまれて末法にあふ。うらむべしといへども…」という言葉から始まります。日本が仏法の本場であるインドから地理的に遠く離れた辺境の地であり、時代としても仏法が衰退した末法であること を嘆いています。
しかし、その厳しい状況にもかかわらず、「仏仏嫡嫡相承の衣法」に出会えたこと を、筆者は計り知れない喜びとして強調しています。
「正伝の衣法」とは何か
「仏仏嫡嫡相承の衣法」とは、単に袈裟という衣と仏法を指すだけでなく、釈尊から正統な後継者へと途切れることなく代々伝えられてきた、本物の袈裟とその教え のことです。
この正伝はインドで釈尊から二十八代、中国で五代を経て曹谿山の六祖慧能禅師に至り、その後も代々受け継がれてきた と記されています。
この袈裟は、単なる布で作られた衣ではなく、「如来の皮肉骨髄を正伝せる」 ような、仏法の真髄が宿るものと見なされています。
中国で新たに作られた袈裟や、正伝を受けていない師から伝えられた袈裟 とは異なり、特別な価値を持つものとされています。唐の代宗皇帝も、この正伝の仏衣を国の宝として扱い、厳重に守護するよう命じていたほどです。
袈裟に込められた計り知れない功徳
袈裟は、単なる修行僧の制服ではありません。それは 「仏弟子の標幟(ひょうし)」、つまり仏弟子であることの目印です。そして、袈裟には多くの功徳があると説かれています。
袈裟は古くから 「解脱服」 と呼ばれ、過去の悪行による障り、煩悩による障り、悪行の報いによる障りなど、あらゆる苦しみから解脱できる力 があるとされています。
また、袈裟は 人天(人間や天人)、龍神などからも重んじられ、守られる もの。袈裟を敬うことで 多くの罪が滅し、多くの福徳が生じる とされ、煩悩から身を守る 「金剛の真甲冑」 にも例えられます。
驚くべきことに、竜が袈裟の糸一筋を得るだけで災厄を免れたり、牛が袈裟に触れただけで罪が消滅したという話 も紹介されています。
このように、諸仏も成道する際には必ず袈裟を身につける とされ、最尊最上の功徳があることが示されています。袈裟は、在家の人々が受持しても悪鬼が近づけないほどの力を持つとも説かれています。
恩を知り、正法を護持する喜び
私たちは、釈尊が生まれた遠いインドから、山や海を越え、過去世からの善行 (宿善) のおかげで、この正法と正伝の袈裟に出会うことができたのです。それは、私たちがこれまでに 無数の諸仏のもとで多くの功徳を積んできた結果 であろうと述べられています。
この奇跡的な出会いを、自分のことではあっても尊び、共に喜ぶべきであり、何よりも 祖師が法を伝えてくれた深い恩 に心から感謝し、その恩に報いるべきであると強く語られています。なぜなら、動物でさえ受けた恩を忘れず報いるのに、人間が恩を知らないならば、動物よりも愚かだからです。
したがって、この正法と袈裟に出会えたならば、日夜修行に励み、袈裟を常に大切に身につけ (頂戴護持) すること が、私たちに与えられた恩に報いる道なのです。それは、たとえ無数の命を捨ててでも供養すべきほどの、計り知れない価値がある行為なのです。
問いかけとまとめ
この記事を通じて、皆さんは袈裟が単なる「衣」以上の、深い意味と計り知れない功徳を持つ「宝」であること、そして、それが遠い昔、遠い国から、多くの仏祖の願いと恩によって現代の私たちに伝えられた奇跡であることを知っていただけたかと思います。
私たちの身近にある仏教や仏教の道具(袈裟、お経、仏像、お寺など)は、全てこの尊い正法の一部です。それらに触れる機会があること自体が、実は大変ありがたいことなのです。
皆さんは、日々の生活の中で、この仏法の「恩」を感じることがありますか?祖師が命がけで伝えてくれた教えや、今ある仏教文化に対して、どのような気持ちを持つことができるでしょうか。
この機会に、身近な仏教に改めて目を向け、その背景にある深い歴史と多くの功徳、そして私たちに法を伝えてくださった方々への感謝の気持ちを持ってみるのも良いかもしれません。
さて、冒頭のクイズの答えです。恩を知らないとある生き物よりも愚かだとされる、ある生き物とは、A) 畜類(動物) でした。私たち人間は、知恵があるからこそ、恩を知り、感謝し、報いることができるはずです。この教えは、仏道に限らず、私たちの日常生活においても、常に心に留めておきたい大切なメッセージですね。
この記事が、皆さんの仏教への理解を深め、日々の生活の中で「恩」や「ありがたさ」を感じるきっかけとなれば幸いです。