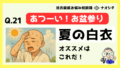直七法衣店4代目ナオシチです。今日もみんなで袈裟功徳について学んでいきましょう。
3択クイズにチャレンジ!答えは最後に。
仏教において「袈裟」は、古くから何と呼ばれてきたでしょう?
A. 悟りの衣
B. 解脱服
C. 仏の証
原文
道元禅師の著した『正法眼蔵』「袈裟功徳」の巻より、一部を引用します。
印度、震旦、正法、像法(ゾウホウ)のときは、在家なほ袈裟を受持す。いま遠方辺土の澆季(ギョウキ)には、剃除鬚髪(テイジョシュホツ)して仏弟子と称する、袈裟を受持せず、いまだ受持すべきと信ぜず、しらず、あきらめず、かなしむべし。
いはんや体色量(タイシキリョウ)をしらんや。いはんや著用の法をしらんや。袈裟はふるくより解脱服と称す。業障(ゴッショウ)、煩悩障(ボンノウショウ)、 報障等、みな解脱(ゲダツ)すべきなり。
龍もし一縷(イチル)をうれば、三熱をまぬかる。牛もし一角にふるれば、その罪おのづから消滅す。諸仏成道(ショブツジョウドウ)のとき、かならず袈裟を著(ヂャク)す。しるべし、最尊最上の功徳(クドク)なりといふこと。
現代語訳
釈尊の教えが正しく伝わっていたインドや中国の時代には、在家の人々でさえ袈裟を受けて大切に身につけていました。
しかし、今日、遠く離れた辺境の地である日本の末法の時代には、髪やひげを剃って仏弟子だと名乗る者でさえ、袈裟を身につけず、身につけるべきだと信じず、知ろうともせず、明らかにしようともしません。これは悲しむべきことです。
ましてや、袈裟に使う布の種類や色、形、大きさといった「体色量」を知っているでしょうか。さらに、正しい着用方法を知っているでしょうか。いいえ、それすらも知らないのです。
袈裟は古くから「解脱服(げだつふく)」と呼ばれています。これを身につければ、過去の悪い行いによる障り(業障)、貪り・怒り・愚かさといった煩悩による障り(煩悩障)、そしてその報いとして苦しみを受ける障り(報障)などから、すべて解き放たれる(解脱する)ことができるのです。
龍でさえ、もし袈裟の糸一本でも身につければ、龍を苦しめる三つの熱さから逃れることができます。牛が、もし袈裟の角に触れさえすれば、その罪は自然と消え去ると言われています。
また、すべての仏が悟りを開く(成道する)時には、必ず袈裟を身につけています。このことから、袈裟には最も尊く最も優れた功徳があるということを知るべきです。
語句説明
- 印度(いんど):インド
- 震旦(しんたん):中国の古い呼び名
- 正法(しょうぼう):釈尊の正しい教えがそのまま行われている時代
- 像法(ぞうほう):正法の次に、釈尊の教えの形は残っているが行いは衰える時代
- 辺土(へんど):中心地から遠く離れた土地。ここでは日本を指す
- 澆季(ギョウキ):末法の時代。教えが薄れ、人々の心がすさんだ時代
- 剃除鬚髪(テイジョシュホツ):髪やひげを剃ること。出家者の姿
- 受持(じゅじ):受け取って大切に保つこと。ここでは袈裟を身につけ護持することを指す
- 体色量(タイシキリョウ):袈裟の素材(体)、色(色)、大きさ(量)に関する定め
- 著用の法(ヂャクヨウノホウ):袈裟の身につけ方、着用方法
- 解脱服(げだつふく):解脱の功徳を持つ衣のこと。袈裟の別称
- 業障(ゴッショウ):過去の行為によって引き起こされる障り
- 煩悩障(ぼんのうしょう):貪り、怒り、愚かさなどの煩悩によって引き起こされる障り
- 報障(ほうしょう):悪業の報いとして受ける苦しみによる障り
- 三熱(さんねつ):龍が受ける苦しみとされる三つの熱さ。出典は『海龍王経』とされる
- 成道(じょうどう):悟りを開くこと
詳細な解説
袈裟の受持 – 過去と現代のギャップ
この原文を読んで、まず驚かされるのは、かつてインドや中国では在家(出家していない一般の人々)でさえ袈裟を大切に身につけていたという記述です。現代の日本では、袈裟はほとんど僧侶だけが着用するものというイメージが強いですから、これは意外な事実かもしれません。
それに対して、筆者である道元禅師は、当時の日本の状況を深く嘆いています。せっかく仏弟子として出家し、髪やひげを剃っているにも関わらず、多くの僧侶が袈裟を身につけず、その重要性を信じず、知ろうともしない。これは、釈尊の教えが正しく伝わっていた時代や地域と比べて、日本が「遠方辺土の澆季(遠く離れた末法の時代)」にあるがゆえの悲しい状況だとしているのです。
袈裟の正しいあり方を知らない悲劇
さらに道元禅師は、袈裟そのものに対する知識の欠如を指摘します。袈裟を作るための正しい「体色量」、つまりどのような素材(粗布、絹布など、糞掃衣が最上とされる)、どのような色(青、黄、赤、黒、紫の壊色(くすんだ色)で、釈尊は肉色)、どのような形や大きさ(九種類の大衣や三種の上中下など)を用いるべきかを知らない。また、袈裟をどのように「着用」すべきか(右肩を出す偏袒右肩や両肩を覆う通両肩搭など、五条衣、七条衣、大衣の使い分け)といった「著用の法」も知らない、と重ねて嘆いています。正しい袈裟は、仏祖から代々受け継がれてきたものであり、その伝統を重んじるべきだという考えが背景にあります。
「解脱服」としての袈裟の力
袈裟がなぜこれほど重要視されるのか。それは、袈裟が「解脱服」と呼ばれるほど、計り知れない功徳を持つからです。袈裟を身につけることで、私たちの苦しみの根源である「三障(業障、煩悩障、報障)」から解き放たれることができると説かれています。
この袈裟の不思議な功徳を示すのが、龍と牛のたとえ話です。
- 龍の功徳: 龍は仏教では特別な存在ですが、苦しみも伴います。しかし、袈裟の糸一本でも身につけるだけで、龍を悩ませる三つの熱い苦しみから逃れることができるというのです。
- 牛の功徳: 牛が袈裟の角に触れただけで、その罪が消滅するとも言われます。
このように、袈裟はたとえその一部であったり、触れるだけであっても、衆生に大きな利益をもたらす「最尊最上の功徳」を持っているとされているのです。袈裟は、見る者を歓喜させて邪心を遠ざけたり、身につける者に福を生み罪を滅したり、煩悩を断ち切り智慧の剣として働く など、さまざまな神力を持つと説かれています。
仏が成道時に着ける衣
そして、この袈裟の重要性を決定づけるのが、「諸仏が成道する時に必ず袈裟を著す」という事実です。過去、現在、未来のすべての仏が悟りを開くという最も神聖な瞬間に、必ず袈裟を身につけている。これは、袈裟が単なる衣服ではなく、仏となるための、あるいは仏であることの証であり、その功徳がいかに偉大であるかを示す、揺るぎない根拠であるとされているのです。
あなたにとって、袈裟とは?
今回の原文を通して、袈裟が仏教においていかに重要で、深い意味を持つ存在であるかを知ることができました。単なる布切れではなく、「解脱服」として私たちを苦しみから救い、仏となる道を助ける「最尊最上の功徳」が込められているのです。
現代に生きる私たちは、袈裟を身につける機会は少ないかもしれません。しかし、この袈裟に込められた願いや功徳を知ることは、日々の生活や信仰、あるいは日本文化に対する見方を変えるきっかけになるのではないでしょうか。
あなたにとって、袈裟はどのように見えますか? この特別な衣について、少しでも関心を持っていただけたら嬉しいです。
クイズの正解は「B. 解脱服」でした。