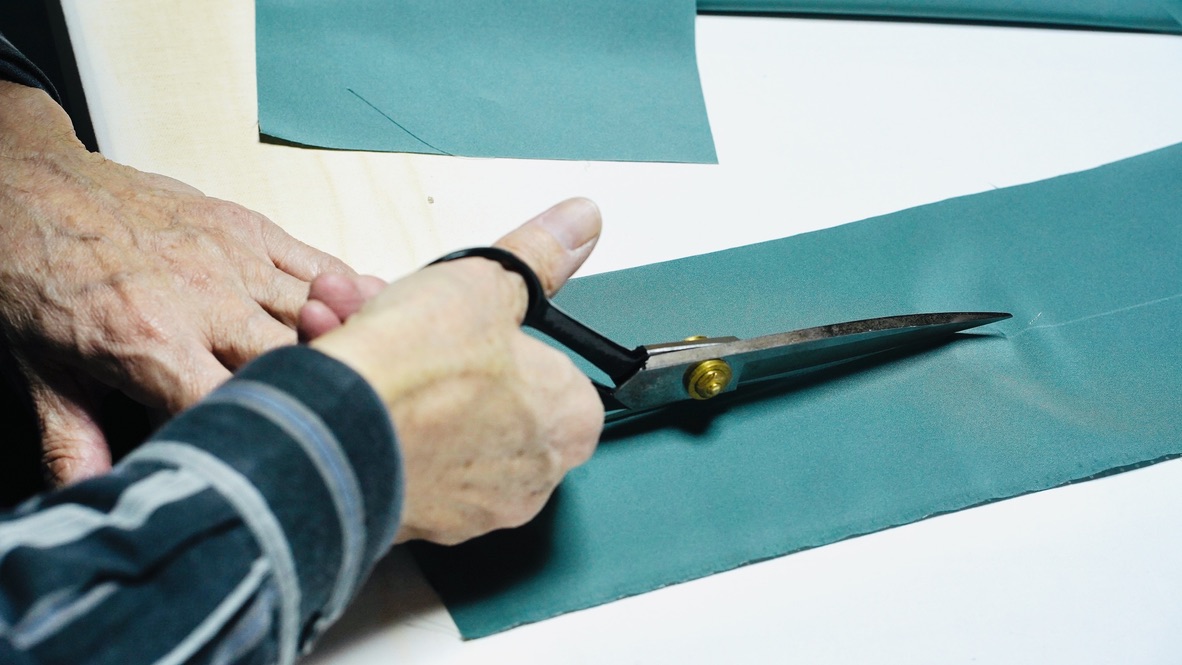直七法衣店4代目ナオシチです。今日もみんなで袈裟功徳について学んでいきましょう。
3択クイズにチャレンジ!答えは最後に。
唐の代宗皇帝は、袈裟を「国の宝」とまで称し、ある寺に送る際、ある人物に「頭の上に頂いて」運ばせました。それはどのような人物だったでしょうか?答えは記事の中に記載しています。
A. 国を代表する高僧
B. 鎮国大将軍
C. 皇帝の血縁者
『正法眼蔵』より ~唐の皇帝と袈裟~
まずは、今回のテーマとなる『正法眼蔵』「袈裟功徳」からの抜粋をご覧ください。
諸代の帝王、あひつぎて内裏(ダイリ)に奉請(ブショウ)し、供養礼拝(クヨウライハイ)す。神物(ジンモツ)護持せるものなり。
唐朝中宗(チュウソウ)、粛宗(シュウクソウ)、代宗(ダイソウ)、しきりに帰内供養(キダイクヨウ)しき。奉請のとき、奉送(フソウ)のとき、ことさら勅使(チョクシ)をつかはし、詔(ショウ)をたまふ。
代宗皇帝、あるとき仏衣を曹谿山におくりたてまつる詔にいはく、「今、鎮国大将軍 劉崇景(リュウスウケイ)をして頂戴して送らしむ。朕(チン)、之(コレ)を国の宝と為す。卿(ケイ)、本寺に安置して、僧衆(ソウシュ)の親しく宗旨を承(ウ)くる者をして厳に守護を加へしめ、遺墜(イツイ)せしむること勿(ナカ)るべし」。
まことに無量恒河沙(ムリョウゴウガシャ)の三千大千世界を統領せんよりも、仏衣現在(ブツエゲンザイ)の小国に、王としてこれを見聞(ケンモン)供養したてまつらん は、生死(ショウジ)のなかの善生(ゼンショウ)、最勝の生(ショウ)なるべし。
現代語訳
過去の多くの帝王たちは、代々、袈裟を宮中にお迎えし、供養し礼拝しました。袈裟は神聖なものとして守り護られてきたのです。
唐の時代の皇帝である中宗、粛宗、代宗は、繰り返し袈裟に帰依し、供養しました。宮中に迎える時も、お寺にお送りする時も、特別に勅使を遣わし、詔(命令書)を出したほどです。
代宗皇帝が、ある時、仏の衣(袈裟)を曹谿山(そうけいざん)というお寺にお送りする際の詔には、次のように述べられています。
「今、鎮国大将軍の劉崇景(りゅうすうけい)に(袈裟を)頭の上に頂いて(敬い)、送らせる。私はこれを国の宝とする。卿(寺の責任者)は、この袈裟を寺に安置し、教えを正しく受け継ぐ僧たちに厳重に守護させ、決して失ってはならない。」と。
実に、数えきれないほど広大な世界を治めることよりも、仏の衣(袈裟)が今現在ある小さな国(日本)で、王としてこれを見たり聞いたり、供養したりできることの方が、迷いの世界(生死)における良い生まれ変わり、最も優れた生であるに違いない。
語句説明
- 奉請(ぶしょう)、供養礼拝(くようらいはい): 敬って迎えること、仏や僧などに供え物をして敬い拝むことを指します
- 神物(じんもつ): 神聖なもののことです。ソースでは袈裟は仏そのもの、「仏身」「仏心」であるとも述べられています
- 帰内(きだい): 帰依し、尊重すること
- 勅使(ちょくし)、詔(しょう): 皇帝の命令を伝える使者、皇帝の命令書です
- 頂戴(ちょうだい): 頭の上に載せて敬うこと。ソースでは、袈裟を頭の上に載せて敬う行為を指します
- 曹谿山(そうけいざん): 中国の霊山で、特に禅宗にとっては重要な聖地とされています
- 僧衆(そうしゅ): 僧侶たちの集まり
- 宗旨(しゅうし): 宗教の教え、特にその最も重要な教えのこと
- 遺墜(ゆいつ): 失い、落とすこと。ここでは、袈裟を大切に守り伝えることの裏返しとして使われています
- 無量恒河沙(むりょうごうがしゃ): 数えきれないほどの非常に多い量を表します。「ガンジス川の砂の数ほど」という意味です
- 三千大千世界(さんぜんだいせんせかい): 仏教の世界観において、非常に広大で無限ともいえる宇宙全体を指します
- 統領(とうりょう): 統率し、治めること
- 仏衣(ぶつい): 仏の衣のこと。ここでは袈裟を指します
- 小国(しょうこく): この文脈では、日本を指しています
- 生死(しょうじ): 生まれては死に、死んでは生まれるという、仏教における迷いの世界のことです
- 善生(ぜんしょう): 良い生まれ変わり
- 最勝の生(さいしょうのしょう): 最も優れた生まれ変わり、最高の生を意味します
詳細な解説:なぜ皇帝は袈裟を「国の宝」とまで称えたのか?
さて、唐という大帝国を治める皇帝たちが、なぜここまで袈裟を大切に扱ったのでしょうか。
『正法眼蔵』では、袈裟は「諸仏の恭敬(くぎょう)帰依しましますところなり。仏身なり、仏心なり」と説かれています。
つまり、袈裟は単なる衣服ではなく、仏さまそのものであり、仏さまの心そのものである、と捉えられているのです。そして、過去の仏さまや祖師たちが皆、この袈裟を敬い、依りどころとしてきたものであるとされています。
唐の皇帝たち(中宗、粛宗、代宗)は、このような袈裟の持つ神聖性、仏法そのものであるという性質を深く理解していたのでしょう。だからこそ、袈裟を宮中に迎えたり送ったりする際には、国の威信をかけて勅使を遣わし、特別に詔を発しました。
特に、代宗皇帝が曹谿山にお送りした詔には、「鎮国大将軍の劉崇景(りゅうすうけい)に(袈裟を)頭の上に頂いて(敬い)、送らせる。私はこれを国の宝とする」と明確に記されています。広大な領土や財宝よりも、袈裟こそが国にとって最も価値のあるものだ、と断言しているのです。
そして、それを寺に安置し、正しく教えを受け継ぐ僧たちが「厳に守護」し、「遺墜せしむること勿れ(決して失ってはならない)」と、その重要性を繰り返し強調しています。
この曹谿山は、中国禅宗において非常に重要な場所です。インドから禅を伝えた達磨大師から始まり、六祖慧能へと受け継がれた「正伝の袈裟」が安置されていたと伝えられています。
この「正伝」とは、師から弟子へと仏法が確かに伝えられた証であり、単に形を受け継ぐだけでなく、仏法の真髄が込められた袈裟のことです。
唐の皇帝が曹谿山に袈裟を贈ったのは、この禅宗の正伝の袈裟に対する深い敬意と、その保護への強い意志の表れと言えるでしょう。
そして道元禅師は、この唐の皇帝のエピソードを引き合いに出し、遠く離れた辺境の「小国」である日本に生まれながら、この仏衣(袈裟)、すなわち正伝の法に巡り会えたことを、無上の喜びとして語ります。
彼は、広大な世界を治めることよりも、この日本という小さな国で、王としてこの仏衣を見たり聞いたり、供養したりできることの方が、迷いの世界(生死)における最高の生、最も優れた生まれ変わりであるとまで述べているのです。
これは、正伝の仏法や袈裟が、いかに得難く、尊いものであるかを示しています。ソースの中では、他の国の人々もこの袈裟を深く願い求めている様子が描かれています。
さらに、袈裟を身につけること、護持することには、大きな功徳があると説かれています。袈裟は、解脱の服であり、煩悩の毒矢も害することのできない堅固な金剛の甲冑に例えられます。
袈裟を着ければ、すべての仏が守り助けてくださり、天人からも供養されるとも言われます。
たとえ戒を破るような者であっても、一瞬でも袈裟や三宝(仏・法・僧)を敬う気持ちがあれば、将来仏になることが保証されるという話や、袈裟の一筋の糸を身につけるだけで災難を免れるという話も紹介されています。
また、袈裟は修行そのものを象徴するものであり、袈裟を身にまとうことで、内面から自然と修行の姿(猛利恆修)が生じてくるとも考えられています。袈裟を師や仏舎利の塔のように敬い、毎日頭に載せて偈(げ)を唱えるといった作法も大切にされてきました。
そして、袈裟の材質や作り方も、厳密な伝統があります。本来は捨てられたぼろ布(糞掃衣)を拾い集めて作るのが最も清浄とされ、縫い方も返し縫いが基本とされています。見た目の豪華さや世間の価値観とは真逆の場所に、袈裟の真の価値が見出されているのです。
このように、袈裟は単なる布ではなく、仏法そのもの、修行の道、そして悟りへの確かな導き手として捉えられています。唐の皇帝たちが国の宝としたのは、この袈裟に宿る計り知れない力と功徳を理解していたからに他なりません。
問いかけとまとめ
今回、『正法眼蔵』の「袈裟功徳」から、唐の皇帝たちが袈裟をいかに尊び、「国の宝」としたか、そして、それが私たちにどのような価値を教えてくれるかを見てきました。広大な世界を治めるよりも、小さな国で正伝の仏衣に会えることの方が最高の生であるという禅師の言葉は、私たちが身近にある仏教や伝統文化の価値を改めて見つめ直すきっかけを与えてくれます。
私たちが普段何気なく目にしている仏具や、地域の伝統行事の中にも、今回ご紹介した袈裟のように、長い歴史の中で大切に受け継がれてきた深い意味や物語が込められているかもしれません。
あなたにとっての「国の宝」、あるいは日々の生活の中にある「大切なもの」は何でしょうか? それに込められた意味や歴史に、思いを馳せてみてはいかがでしょうか。きっと、新たな発見や感動があるはずです。
クイズの正解は「B. 鎮国大将軍」でした。