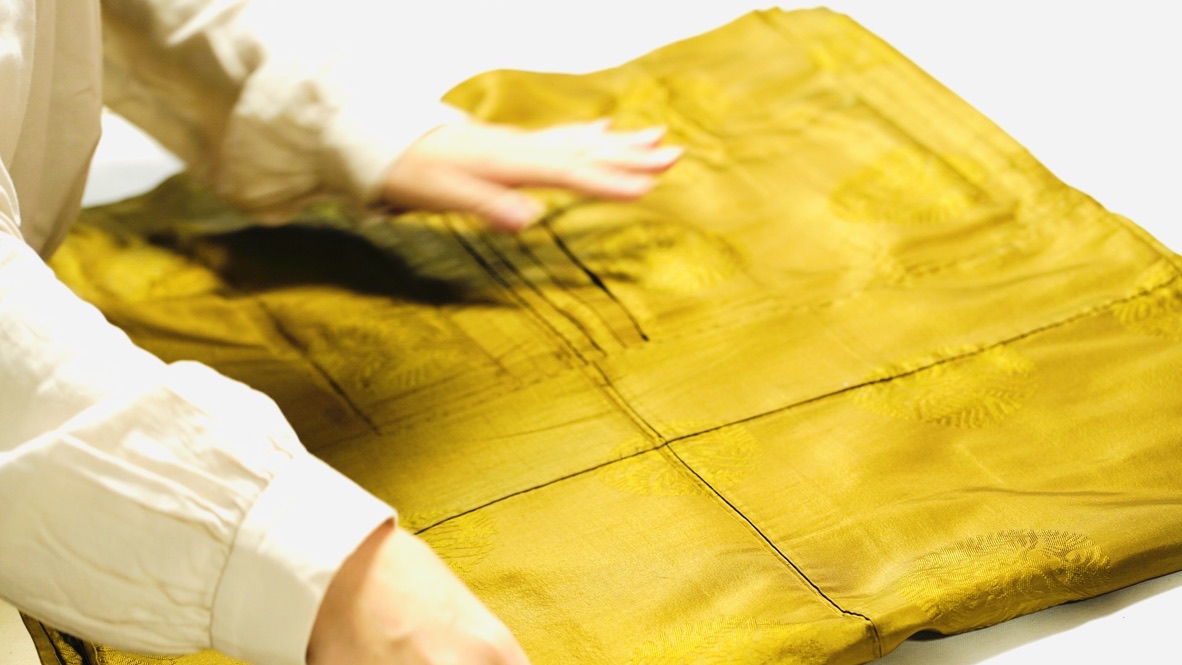直七法衣店4代目ナオシチです。今日もみんなで袈裟功徳について学んでいきましょう。
3択クイズにチャレンジ!答えは最後に。
クイズ:道元禅師が考える「正伝の袈裟」を受け継ぐことは、どのような意味を持つとされたでしょうか?
- 最上の福徳を得て、必ず仏道を悟ることができる
- 身分や賢愚に関わらず、過去世の善根の証となる
- 他宗派の僧侶からの尊敬を集めることができる
原文
「他国の衆生いくばくかねがふらん、わがくにも震旦国のごとく、如来の衣法まさしく正伝親臨せましと。
おのれがくにに正伝せざること、慚愧ふかかるらん、かなしむうらみあるらん。
われらなにのさいはひありてか、如来世尊の衣法正伝せる法にあふたてまつれる。宿殖(シュクジキ)般若(はんにゃ)の大功徳力なり。
いま末法悪時世(まっぽうあくじせ)は、おのれが正伝なきをはぢず、他の正伝あるをそねむ。おもはくは、魔党(まとう)ならん。
おのれがいまの所有(ショウ)所住は、前業(ゼンゴウ)にひかれて真実にあらず。ただ正伝の仏法に帰敬(キキョウ)せん、すなはちおのれが学仏の実帰なるべし。」
現代語訳他国の人々も、この袈裟を、どれほど深く願い求めていることでしょうか。
「我が国にも、中国のように、如来の衣と法が正しく伝わって、親しく見ることが出来ますように。」と。
この衣と法が、自分の国に正しく伝わらないことは、慚愧の心深く、悲しいことでしょう。我々は何の幸いがあって、如来の正しい伝統の衣と法に会うことが出来たのでしょうか。それは、我々が過去世に植えた善根と智慧の、大きな功徳の力によるものなのです。
今の末法の悪世では、自分に正しい伝統の衣と法が無いことを恥じないで、他の人には正しい伝統の衣と法があることを妬むのです。思うに、その者は仏道を妨げる魔物の類でしょう。
自分が今所有しているものや、住している所は、自らの前世の行いの影響を受けて、真実のものではありません。ですから、ひたすら正しく伝えられた仏法を敬い帰依することが、自ら仏道を学ぶための真実の帰処なのです。
語句説明
- 震旦国(しんたんこく): 中国
- 衣法(えほう): 袈裟と法
- 正伝(しょうでん): 正しく伝えられた伝統
- 慚愧(ざんき): 恥じる心、後悔する心
- 宿殖般若(しゅくじきはんにゃ): 過去世に植えられた善根と智慧
- 末法悪時世(まっぽうあくじせ): 仏法が衰退し、乱れる末世の時代
- 魔党(まとう): 仏道を妨げる魔物の類
- 前業(ぜんごう): 過去世の行い
- 帰敬(ききょう): 敬い帰依すること
詳細な解説
道元禅師の危機感と自負
道元禅師は、当時の日本を「遠方辺土の澆季(末世)」と捉え、仏法が正しく伝えられていない現状を深く嘆きました。
彼が見た中国では、多くの学者が経典の講義を捨てて、自ら進んで仏祖が伝えた正法を学び、従来の弊衣を脱いで仏祖正伝の袈裟を受け継いでいました。しかし、日本では僧侶でさえ袈裟を護持せず、その意味を知らない者が多かったのです。
この状況に対し、道元禅師は強い自負と使命感を抱いていました。
彼自身が中国の如浄禅師から受け継いだ袈裟こそが、釈迦牟尼仏から続く58代目の嫡嫡相承の仏法の証であり、その衣法(袈裟と法)を日本に伝え、広めることが自らの役割であると考えていました。
彼にとって、日本の僧侶が袈裟の正伝を知らないことは「慚愧ふかかるらん、かなしむうらみあるらん」と、深い悲しみを覚える事態だったのです。
袈裟は仏法そのもの
道元禅師は、袈裟が単なる衣類ではないことを繰り返し説いています。袈裟は「諸仏の恭敬帰依しましますところなり。仏身なり、仏心なり」。つまり、袈裟は仏法の精髄であり、仏の身体や心そのものと見なされるほどの尊い存在なのです。
袈裟には様々な呼び名があります。「解脱服」「福田衣」「無相衣」「無上衣」「忍辱衣」「如来衣」「大慈大悲衣」「勝幡衣」「阿耨多羅三藐三菩提衣」など、これらの名前はすべて、袈裟がもたらす広大な功徳と、仏法の真実を表現する象徴としての意味を表しています。
袈裟を身につけることは、悪行による障り、煩悩、悪報などから解脱できると説かれ、さらには龍や牛といった動物でさえ、袈裟に触れることで罪を消滅させ、悟りを得る因縁となるという逸話も紹介されています。
形が内面を作り、本質を保証する
道元禅師は、袈裟の材質や縫い方、着用方法に至るまで、細かく規定された「正伝の作法」を重視しました。彼の思想では、形(外観)が本質を保証し、内面を作り出すという考え方が強くあります。
たとえ一瞬でも袈裟を身につければ、「無上菩提」への護身符となる。修行者の猛烈な修行の力ではなく、袈裟の功徳自体が不思議な神力を持つとされます。
これは、現代の私たちにも通じる教えです。例えば、制服やユニフォームを身につけることで、その役割や責任を自覚し、行動が変化するように、袈裟という形を大切にすることで、仏道にふさわしい心構えが自然と育まれるという洞察です。
道元禅師は、たとえ戯れに袈裟を着けた者でも、三生のうちには仏道を悟る因縁となる、とまで語ります。
「宿善」と「末法の悪世」
道元禅師は、自分が「如来世尊の衣法正伝せる法」に出会えたことを「宿殖般若の大功徳力」、すなわち過去世に植えた善根と智慧の力によるものだと喜びました。
そして、まだ袈裟を得ていない者には、今生の中で急いで善根の種を蒔くように勧め、それができない者には、諸仏や三宝に慚愧懺悔(ざんきせんげ)するように説きました。
彼が活動した時代は、仏法が衰退し、正しい教えが失われつつある「末法悪時世」と考えられていました。
そのような時代に、自分に正しい伝承がないことを恥じず、他者が正伝を持つことを妬む者は「魔党」であると厳しく批判しています。これは、単なる他宗派への批判だけでなく、仏道を志す者自身の内なる迷いや傲慢さへの警鐘とも解釈できます。
道元禅師は、私たちが現に所有し、住んでいる世界が「前業にひかれて真実にあらず」、つまり過去の行いの影響を受けている不確かなものであると指摘し、ひたすら正伝の仏法を敬い帰依することこそが、真の仏道への帰依であると結んでいます。
問いかけとまとめ
道元禅師の言葉からは、仏法の真髄を受け継ぎ、次世代に伝えようとする並々ならぬ情熱が伝わってきます。彼は、袈裟という「形」を通して、人々の内面に宿る仏性(仏になれる可能性)を呼び覚まし、真の仏道へと導こうとしました。
現代の私たちもまた、日々の生活の中で、何をもって「真実」とし、何を「帰依」すべきか、という問いに直面することがあります。道元禅師の教えは、目に見える形を軽視せず、そこに込められた深い意味と伝統を敬うことの重要性を教えてくれます。
あなたにとっての「正伝の仏法」とは何でしょうか? そして、それをどのように日々の生活に取り入れ、未来へと繋いでいきたいですか?
クイズの答え
A. 最上の福徳を得て、必ず仏道を悟ることができる
解説: 道元禅師は、「正伝の袈裟」を身につけ、護持することは、まさに無上の悟り(阿耨多羅三藐三菩提)を成就する「護身符」となると説いています。
たとえ一時的に戒を破ったり、戯れに着用したとしても、それは将来必ず仏道を悟る因縁となると強調されています。